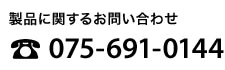観修寺

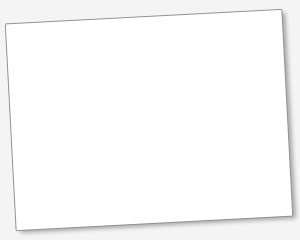
かなりジメジメした日が多くなり、
早くもバテ気味な感じです。
ですが、
まだ暑くなっていくのはこれからという事で、
夏バテしないようにしないとなぁと思いつつ、
今夜の食事はそうめんにしようかな。
と、確実に夏バテする道を進行中の
製造部の伊賀です。
さて、今回ご紹介するのは
京都市山科区にある「観修寺」です。
読み方は「かじゅうじ」と読むのですが、
この辺りの地名の呼び方は
「かんしゅうじ○○町」と読むので
自分も行ってみるまで
正式な読み方を知りませんでした。
ここ観修寺は昌泰3年(900年)、
醍醐天皇が創建され
千有余年の歴史があります。
中門を入ると直ぐ右手に
堂々とした宸殿が芝生越に見えます。
宸殿の北にある書院は
公開されていないので入れませんが
明治維新直後、一時的に
京都府郡部最初の小学校に使われたという事があった為か
縁側で読書をしている人がいたりとして驚きました。
書院の南の平庭には、
一面に樹齢750年と伝える偃柏槙(ハイビシャクシン)が
地を這うように枝を広げており、
その中に雪見型をアレンジして創作された
ユニークな形の灯篭は
勧修寺型と灯篭といわれ、
水戸光圀公が寄進されたものです。
庭園は、京都市の名勝にも指定されている所で
平安時代初期のものとされる氷室池を中心にした
池泉回遊式庭園と、
書院南にひろがる庭の二つから成っている。
氷室池越しに南大日山の稜線が迫り、
醍醐の山々が望め、奥行きのある空間が見事で
四季の自然美と
人工の構成美を兼ね備えた景色が広がっています。
この時期は丁度花菖蒲、睡蓮、ハス等が咲いていて
氷室の池を賑わせていますし、
水鳥の隠れ家としても有名ですので
自然と人工の織り成す庭園を是非見に来てください。
| « 前の記事 | 記事一覧に戻る | 次の記事 » |

-thumb-300xauto-816.jpg)